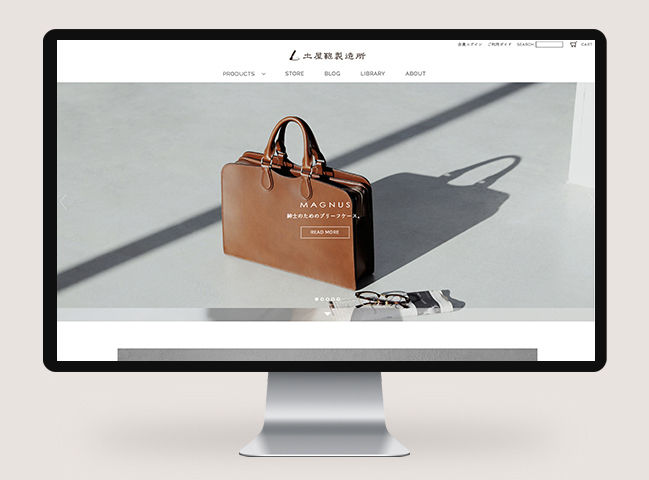ITベンチャーから市役所へ異例の転身
「神戸市」と聞いて、皆さんはどのようなイメージを抱かれるでしょうか。西洋文化が古くから花開いた異国情緒あふれる港町という印象を持つ人もいるでしょう。また、六甲山や摩耶山から見下ろす美しい夜景は観光スポットとして全国的に知られています。
こうした神戸市の魅力を伝えるべく、「PRプランナー」として広報戦略部で働いているのが大橋秀平さん。実はデジタルマーケティングのベンチャー企業での勤務経験があるなど異色の経歴の持ち主なのです。
「ちょうど転職を考えていた時期にWantedlyで神戸市の人材公募を見て応募しました。私は関東の出身で神戸に縁もゆかりもなかったのですが、これまでのPRの経験が活かせるのではないかと思ったのです」
2019年6月より業務を開始した大橋さん。現在は週3日を神戸市で、残りは東京で民間企業のPRやマーケティングを掛け持ちで取り組む日々。
神戸市のPRプランナーとしての仕事は3つあり、1つ目は市長肝いりの施策のプロモーション計画と実施、2つ目は各部局のアドバイザーとしてPRの研修や相談に応じること、3つ目はプランナーとしてのプロジェクトを企画立案し、推進することです。
魅力ある大都市でも人口が減っている
大橋さんのように行政とはまったく異なる業種からの人材を受け入れ、嘱託制度を利用して副業(複業)を認めるなど、かなり変わった制度を運用している神戸市ですが、その背景には切実な問題がありました。
市の中心部である三宮の賑やかな様子を外から見る限りでは、近年注目を集めている「地方創生」の話題とは無縁のようにも感じられます。しかし、さまざまな人口調査などからは、神戸市もまた少子高齢化による人口減少と若年世代の大都市部への流出という大きな課題があったのです。
全国で20カ所ある人口50万人以上の政令指定都市のうち、かつては横浜市、名古屋市、京都市、大阪市と並ぶ五大都市として名を連ねていたいた神戸市ですが、2019年には川崎市に順位を逆転され7位になり、また、総務省が公表した人口動態調査においては、前年比6,235人減(日本人のみ)という全国でもワースト1という人口減少数となりました(01)。
もちろん神戸市としても手をこまねいていたわけではありません。現在「神戸創生戦略」を掲げ、2020年までの5カ年計画である「神戸2020ビジョン」と一体として人口減少時代へ向けた具体的な施策を進めています。
対策事業の内容は多岐に渡りますが、安定した雇用の創出や若い世代の結婚・出産・子育て・教育を支援する環境づくりは特に重要な要素です。
大橋さんはPRプランナーという立場からこの課題に挑むことになりました。しかし、民間から行政という転職のため、働き方の違いに戸惑うことも。
「週3回勤務ということもあり、時間感覚の違いはありました。また外資系での勤務経験から、業務上の機会損失=マイナスの評価というイメージが強く身についていたため、自らチャンスを取りに行く努力をしてきましたが、チャンスを捉える(もしくは捉えようとする)ことが苦手な職員が思ったよりも多かったことには驚きました」
ヨソモノの視点で神戸の魅力を見いだす
PRプランナー就任からまだ日が浅いということもあり、現在は情報収集と、移住・Uターン・企業誘致など関連する部局との調整、プロモーションの計画づくりなどを慌ただしく同時進行で行なっているという大橋さん。しかし、いくつかある手段のうち、SNSプロモーションの重要性は感じていると言います。
「神戸市を若者が住みたいと思える街にするには制度面の充実を前提としますが、魅力を確実に届けていくにはTwitterやFacebook、InstagramといったSNSを有効に活用しない手はありません。幸いなことに、すでに公式FacebookページはもちろんTwitterやInstagramのアカウントも運用されています。これとまちおこしの活動を連携させていければと思います。また、公式Webサイトも生活情報を求める市民からのアクセスが多くありますし、こうした領域でも前職の経験や知恵を生かしていけるのではないかと考えます」(02)
副業的なスタイルで神戸市の仕事に取り組んでいる理由について尋ねると、地方自治体のPRを考えていくうえでは外部の視点を常にフレッシュに保つことにメリットがあると言います。
「もちろん、ここ(神戸市)に住んでしまえば、移動の時間は減って仕事の時間は確保しやすくなるかもしれません。しかし、地元の人にとってはごく当たり前と思っていることや、PRする必要を感じていない本当の魅力を発見して伝えていくためには、外から来たヨソモノ視点が必要だと思います。神戸市は歴史的に見ても外から訪れた人を寛容に受け入れる土壌があります。その意味ではとても仕事がやりやすい環境です」

ステークホルダーは150万を超える神戸市民
民間企業の仕事から一転して地域の仕事に関わっていくことで、大橋さんの中でも心境の変化が生じつつあるといいます。
「以前の仕事ではクライアントがいて、サービスの利用者がいて、ステークホルダー(利害関係者)は比較的はっきりとしていたので、それ以外のことを考える必要はあまりありませんでした。しかし、市のPRという仕事は、まず目の前に約2万人の市職員、そしてその先には多くの市民の生活があります。つまり、およそ150万人を超える神戸市民全員がステークホルダーということになります。非常に大きな責任があるとともに、やりがいのある仕事だと日々感じています」
神戸市としても情報発信だけでなく、さまざまなチャンネルで市民とのコミュニケーションを図っていますが、本質的には市民の当事者意識をどのように高めていくかということが一番大きな課題になってくると言います。
「これは個人的な見解で確かな根拠はありませんが、地方をめぐるさまざまな課題の根本的な原因は、自分たちが街を動かしているのだという自負や当事者意識の不足なのではないかと考えています。神戸市は郷土愛が強い地域だと感じていますが、これを単なる驕りではなく『シビックプライド(市民としての誇り)』へと高めていくこと、経済的な尺度に限らず地域特有の価値を自ら見出していくことが求められているのではないでしょうか」
地方のプロモーションはすでに次のステージに差し掛かっているという大橋さん。課題解決のために外部の知恵を積極的に活用している神戸市での取り組みはまだ特殊な例なのかもしれませんが、大橋さんのような働き方、実際に住まなくてもその地域の当事者として深く関わるというつながり自体が「関係人口」のモデルケースとなり得るかもしれません。