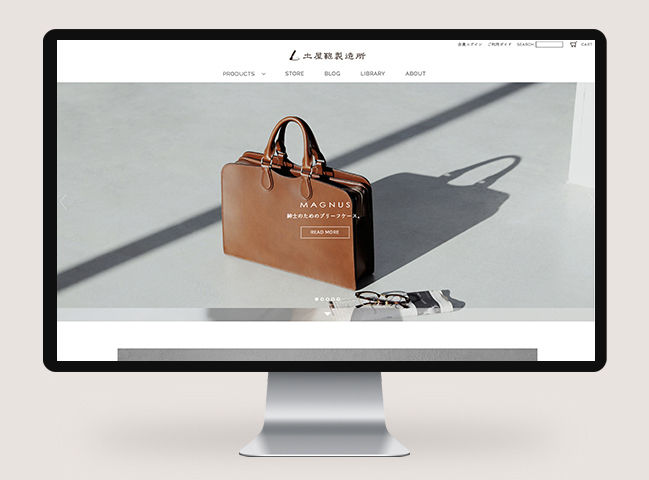SWOTを捨てて逆転の発想を持つ
日本の地方は第二、第三のシリコンバレーになる?
地域の活性化のためのコンサルティングなど、さまざまな事業を手がけるクリエイティブ・エッジは、東京の大手企業で働いていた村中克成さんが、地元である福井に戻って立ちあげた会社です。そもそも村中さんが地方の仕事に携わるようになったのには2つのきっかけがあったと言います。
「一つは90年代の終わりにシリコンバレーに出向して働いた経験です。世界のIT技術をリードするシリコンバレーに行ってみたら、“車で1時間も行けば海や山が楽しめる環境だからイノベーションが育つ”と自慢している。日本の田舎との差はどこにあるのだろうと気になりました。もう一つは地方創成の仕事に携わっていたときに、東京で熱く語られる地域振興策の多くが、実は地域から外に出る手助けをしているだけなんじゃないか、と思ったことです。東京の成功モデルをミニチュアにして地方にあてはめているだけ。まるで“地方”という単一のエリアがあるような発想はおかしいと感じたんです」
一石を投じられないか、考えた村中さんは移住促進や観光振興などで、地方の課題解決に携わるようになります。
なぜ「ゆるキャラ」や「B級グルメ」に行き着いてしまうのか
「地方」に大きな可能性を感じているという村中さんですが、一方で、そのポテンシャルをうまく発揮できない現実があると感じていると言います。
「例えば、それぞれの地域が自己アピールをするような事例を考えてみると、ゆるキャラにB級グルメ、そしてインスタスポットと、皆同じになってしまう。風土も土地がらも何もかも違うのに」
なぜだろうと考えて行くうちに「発想の仕方」そのものが悪いのではないかと思いつきます。
「マーケティングにも使われるSWOT分析に、皆が囚われているのではないかと」
SWOTから導かれる戦略では、S(強み)を重視し、W(弱み)を切り捨てがちですが、村中さんはそこに問題があると考えました。
「あまり議論されることはないのですが、地方で弱みとなる部分を切り捨てていったら残るものはだいたい同じです。山や海がすばらしい、水がきれい、お米がうまい…。これだとどうしも没個性、横並びになってしまう」
そこで村中さんは、W(弱み)をS(強み)にひっくり返して(=turn around)捉え直す「StW」(シチュー)という考え方を提唱します。
「地域の“弱み”は、実は土地固有のもので、個性的なものが多いんです。その部分をうまく強みに転換できれば他にない個性になると考えたのです」
発想のもとになったひとつが、クリエイティブ・エッジが映像制作などで協力した新潟県見附市の事例。市町村大合併の流れに乗らなかった見附市は、“小さな自治体”のまま取り残されてしまったのですが、それを強みと捉え直し、「コンパクトシティ」という施策に結びつけ、全国からの注目を浴びたのです。
個性を見つけ出すための「外から」の視点
外から参加するクリエイターにしかできないこと
こうしたStWの過程では、“外からの視点”が活きると言います。
「もちろん、地元の方にもそうした考えを持っている方もいらっしゃるとは思います。しかし、地方に住んでいると、『弱みを切り捨てたい』と考えるようになり、それを活かそうという考え方に目が向かないことが多いのです。そこで力を発揮するのが他地域の制作会社やクリエイターの、客観的な視点です」
ただし、地元の弱みに触れるとなると、相応の説得力が必要となります。そんなことが外部の人間に可能なのでしょうか。
「確かに、よそから来た人間が地元の課題に深く関わるとなると、その立ち位置が問われることがあります。『君は我々の味方なのか、そうでないのか』と。こうした二項対立の状態になってしまうと、話を聞いてもらえないどころか、信頼を失ってしまうケースもありえると思います。話をしっかりと聞いてもらうためにも、トラブルを避けるためにも大事なのは、まず客観的な視点を持つこと、そして“敵味方”とは違う軸から意見を述べていることをわかってもらうことだと思います」
そのためには、「第三極を意識することが大事」と村中さんは言います。
「例えば東京からやってきて、福井のあるエリアの課題解決に協力する場合、東京とそのエリアに加え、三箇所めの視点からも意見を言うようにするのです。私の場合は、それがシリコンバレーの視点だったりしたわけです。三箇所めを意識してアイデアを出したり、プランを提案するようにすると、客観性の担保になるだけでなく、二項対立を避ける助けになってくれます」
第三極の場所は自分が関わったことのある「地域」だけでなく、例えば「マーケティング」と「IT」と「農業」といったような、経験の組み合わせから導き出してもいいそうです。地域での仕事に関わる際には意識したい部分です。
これまで切り捨てていたものに注目してみる
地元の人の心を動かす物語を見つけ出そう
StWを意識して、弱みを強みに変える際には、地域の人たちを巻き込むことが重要になりますが、そのためにはある工夫が必要だと村中さんは言います。
「弱みに触れると言うことは、地域の人が目を背けるポイントに手を突っ込むことになります。だからこそ、一緒になって取り組む動機や理由をつくることが大切です。その際に役立つのが、『物語』。人の心を動かすようなストーリーを見つけ出すことができれば、皆が前向きになれるのです」
「物語」の一例として村中さんが挙げたのが、クリエイティブ・エッジが長期プロジェクトとして手がけている、福井県の観光名所「東尋坊」のイメージアップの事案です。映画やサスペンスドラマでしばしば登場し、“自殺の名所”などと呼ばれることもある東尋坊は、知名度こそ高いものの、観光客の滞在時間が短いなどの課題があると言います。
「“ 東尋坊”という名前は、この崖で突き落とされて殺された、昔のお坊さんに由来するものなんですが、その東尋坊、これまでは人の恨みを買うような悪い坊さんだったと言われてきました。しかし調べてみると、それは大きな間違いで、本当は非業の死を遂げた徳の高い僧だったとわかったのです。ならば、その名誉回復のストーリーを広げて行こう、誤解を払拭することで、幸せを味わう場所に変えてしまおうと提案したところ、まず地元の皆さんが賛成してくれた。そして市や県の検討が始まりました。幸せな場所には長くいたいから、滞在時間についての課題も解決できる。菅原道真の天満宮のように、非業の死は観光にマイナスになりません。福井は幸福度日本一の県なのですが、それを実感できる象徴的な場所がなかった。なかったから東尋坊がその場所になれるのです。これも、地元の皆さんの気持ちが動く物語をうまく見つけることができたからだと思います」
これまで切り捨ての発想で見ていた地方が持つ“ 弱み”の中にこそ可能性がある。そうした視点を持つことが、地域をまたいで仕事をする際の、大きなポイントになるのです。

- 村中克成さん
- NTTコミュニケーションズに20年以上在籍し、インターネットの商用化やECビジネス、ICTコンサルティングなどに携わったのち、クリエイティブ・エッジを立ち上げる。StWやUStWCなど地方にフォーカスした独自開発のマーケティングツールを用いて、地方の課題解決に取り組む